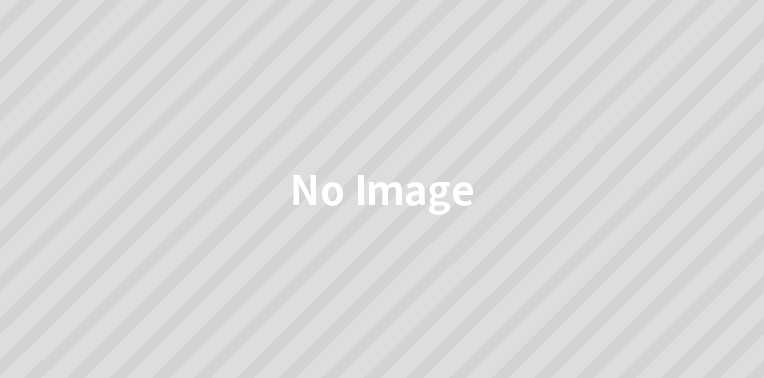誰もがヒーローになれるパラスポーツ KeiDGs×ZEN×GO BEYOND合同開催「ボッチャ大会2025」
- #イベント
- #障がい者
2025.09.12
2025月8月2日、澄みわたった夏の青空のもと、矢上キャンパスで「ボッチャ大会2025」が開催されました。車いすユーザの子どもたちと保護者の皆さん、学生さん、教職員が競うパラスポーツ大会。慶應義塾大学理工学部KeiDGsワーキンググループ(DE&Iに関する委員会)、障がいのある子どもの自立支援活動をする一般社団法人「ZEN」、パラスポーツの普及活動を行う上智大学の学生団体「GO BEYOND」による初の合同開催です。

開会の9時が近づくと、ZENに所属する子どもたちと保護者の皆さん、ZEN代表理事・パラスポーツアスリートの野島弘氏、学生・教職員たちが体育館に集まります。
開会式では、竹村研治郎KeiDGs委員長(機械工学科・教授)から挨拶が述べられ、上智大学のGO BEYONDメンバーがボッチャのルールを説明してくれました。
ボッチャのルールはごく簡単。2チームに分かれて、白球(ジャックボール)をめがけて、1エンドあたり1チーム6球ずつボールを投げます。今回は1試合6エンド(セット)。ボッチャは地上のカーリングとも呼ばれており、ジャックボールに最も近くボールを投げられたチームがそのエンドとボールの近さに応じた点数を手にします。ボッチャは、障がいや体力の有無に関わらず、老若男女が一緒に楽しめるスポーツとして、パラリンピックの正式種目にも加わっています。

まずはGO BEYONDの学生が、ボールを投げてお手本を見せてくれます。単に投げるだけでなく、相手ボールやジャックボールを弾き飛ばし、一発逆転に持ち込む高度テクニックも披露。そのたびにみんなから歓声が湧き上がります。「チームで作戦を工夫してプレーしてください」と必勝アドバイスが伝えられました。

闘志がむくむく湧き上がったタイミングで、始球式へ。ZEN代表理事の野島さんが赤いボッチャボールを天高く投げて大会スタートです。
今回の大会は参加者48名。1チーム6名制で、8チームが総当たりするリーグ戦。年齢・性別も所属も異なる、ごちゃまぜチームの誕生です。メンバー同士で自己紹介をして作戦会議。ボールを投げる順番などを話し合います。

ゲームが始まると、応援する声やかけ声が響きわたり、館内はたちまち熱気で満たされました。子どもたちのプレースタイルは十人十色。車いすを小刻みに動かして投球位置を決め、狙いを定めてボールを投げる慎重派もいれば、サッと投球位置に入って一瞬で投げる直感派も。チームもすぐに打ち解けたようです。いいプレーが出るとハイタッチで喜び合い、失敗すると声をかけて励まします。

ボッチャの面白さは、競技を始めるまで真の実力はわからないところ。小さな子どもが大人顔負けの頭脳プレーをしたり、スポーツが苦手な人が意外と上手だったり、誰でもヒーローになれるチャンスがあるのです。

うまく投げるたびに笑顔やガッツボーズしていた、こうたろうさん(17歳)は「仲間の応援に背中を押されて、ミラクルを連発しました。みんなで話し合って、ピタッと思い通りに投げられた瞬間は楽しかったです」とチームプレーの楽しさを話してくれました。

午前中の前半戦4試合を終えると、ランチタイムへ。理工学部のイノベーション施設「YIL」で、チームや友達同士でお弁当をいただきます。後半戦に向けての作戦会議や反省会、あるいは夏休みの予定や学校の話題でワイワイ盛り上がります。

午後からの後半戦では、勝ちパターンや得意技などチームカラーも生まれ、チームプレーが加速していきます。
毎回真剣な表情で、1球1球を大切に投げていたひよりさん(19歳)は、ボッチャが大好きな女の子。「今年からボッチャを始めて、マイボールも持っています。チームの大学生は私と同じ19歳。ゲームの合間にガールズトークができるのがとっても楽しいです」とはにかんだ笑顔で話してくれました。

16時の試合終了まで、元気に戦い抜いた8チーム。勝ち点の高いチームが優勝チームに選ばれ、表彰式では上位3チームに野島さんから表彰状が手渡されました。
第1回となるボッチャ大会で優勝に輝いたEチームには、熱い拍手と歓声が送られます。Eチームメンバーのサワコさんは「相手ボールを弾くなど姑息な手は使わず、真っ向勝負で臨みました。ジャックボールを味方ボールで囲む戦術を編み出しました。」と勝利の秘訣を話してくれました。

参加したこうたさん(慶應・修士1年)は、「子どもたちのパッションに圧倒されました。小4のときボッチャ経験がありますがた、あのときよりコートが小さく見えました。今日、大人と戦った子どもたちは本当にすごい。ふだん静粛な(?)理工学部が、熱狂と歓声に沸いた夏の1日でした」と、今日の試合をしみじみ振り返りました。
同じチームで健闘したはるかさん(慶應・修士2年)は「年齢も体力も障がいの有無に関係なく、みんなで一つになって楽しめるんだと感じました。子どもたちの移動もお手伝いしましたが、トイレや階段で苦労する場面もあり、今日はさまざまな気づきや発見がありました」と話してくれました。
白熱の大会が終わったあとは、キャンパスツアーに繰り出します。
まずはフィールドロボティクスを研究する石上研究室(機械工学科)の「Test Field」へ。ここでは砂を4トンを入れて月面の疑似環境をつくり、宇宙探査ロボットの研究開発を行っています。四足歩行ロボットが飛んだり、踊ったりする動きに釘づけになった子どもたちからは「すごい!」「生きているみたい」「私も月に行ってみたい!」と声が上がりました。
34棟のマニファクチャリングセンターでは、障がい者と技術の融合をめざす国際的な競技大会であるCYBATHLON(サイバスロン)で活躍した「電動車いす」を披露。世界第3位を勝ち取ったスーパーマシンです。

最後にYAGAMI ART WALL前で記念撮影。理工学部の学生や教職員の思いが描かれた未来のキャンパス。子どもたちが大きくなる頃には、この一部が実現しているかもしれません。
様々な世代や所属、多様な背景や立場の方々が一緒になって楽しんだ「ボッチャ大会2025」。大人も子どもも夏休みを全力で楽しんだ充実の1日でした。

上智大学GO BEYONDのメッセージ
私たちは東京オリンピック・パラリンピックをきっかけに2018年に結成し、パラスポーツを通じて共生社会の実現を目指す活動に取り組んでいます。
パラスポーツの魅力は、障がいの有無、年齢・性別、国籍・人種を超えて、誰もが挑戦でき、おたがいを称え合うことができるのが魅力です。
なかでもボッチャは、誰でも参加して上達できる楽しいスポーツ。今日は、慶應大学理工学部のキャンパスで、皆さんとプレイできたことをとてもうれしく思っています。また、私たちと一緒にパラスポーツを楽しみましょう!

パラスポーツを通じて、誰もが生きやすい社会を目指していこう
野島弘氏(一般社団法人ZEN代表理事)× 石上玄也教授(機械工学科)
ボッチャ大会の合同開催を企画したお二人にお話を聞きました。

野島 石上先生と出会いは、2018年、CYBATHLONの競技で、僕が乗る電動車いすを石上研究室で作ってもらったのが始まりです。
石上 以来、野島さんが主催するイベントに家族で参加させてもらうようになったんです。今回のボッチャ大会は一緒にマス釣りをしながら、「やってみよう!」とひらめいたんですよね。

野島 矢上キャンパスという素敵な場で、スポーツを通じて大学生や教職員の皆さんと触れ合える。これは子どもたちにとって、夏休みの最高の経験になると確信しました。
障がい者が社会で幸せに生きていくには、コミュニケーション力がとても大切です。自分にできないことを誰かに頼んだり、困ったときに助けを求める勇気が人一倍必要なのです。
その力を身につけることができれば、社会で活躍する道も見つかりやすいし、何より生きていて楽しいはずです。子どものうちからパラスポーツを通じて、多くの人たちと心を通わす経験をしてほしいと思い、活動しています。

石上 子どもたちの笑顔が、僕らの心をまたたく間に開いてくれました。学生や教職員とハイタッチするなんて、ふだんじゃ考えられないですから(笑)。障がいのある人が仲間にいると、お互いを思いやる気持ちを素直に表現しやすいんですね。パラスポーツは、みんなの心を一つにする力があるとあらためて感じました。
野島 パラスポーツは、心も体も開放してくれる魅力があります。この輪が広っていけば、障がい者も、健常な人も、みんながもっと生きやすい世の中になると思います。
石上 それぞれの力を発揮して、一緒になって楽しんだ1日でした。この楽しさ、もっと多くの人に体験してほしいですね。ぜひこれからも続けていきましょう!
この投稿をInstagramで見る
この記事に関するお問い合わせはこちら
慶應義塾大学理工学部KeiDGs委員会